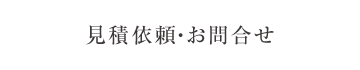トップページ » 不燃木材はホームセンターで買える?価格・種類・DIYでの使い方を徹底解説
不燃木材はホームセンターで買える?価格・種類・DIYでの使い方を徹底解説
「火を扱う場所に木材を使いたいけど安全性が心配」と感じていませんか。
この記事では不燃木材の基礎知識から、身近なホームセンターでの購入可否や選び方、注意点までを専門的に解説します。
そもそも不燃木材とは?ホームセンターで探す前に知りたい基礎知識

不燃木材は特殊な処理で燃えにくくした建材です。
ここでは、その仕組みや法律上の定義、他の木材との性能の違い、そして利用する上での利点と欠点について、基本的な知識をわかりやすく説明します。
不燃木材とは?種類や基準、メリット、難燃木材との違いを徹底解説
不燃木材の定義と仕組み
不燃木材とは、建築基準法で定められた「不燃材料」の性能を持つ木材です。
木材に薬剤を加圧注入するなどの処理を施し、燃焼を抑制する仕組みになっています。
これにより、火災が発生した際に燃え広がりにくくなり、避難時間を確保する役割を果たします。
安全性と木の質感を両立できる建材です。
不燃木材を使うメリット・デメリット
最大のメリットは、法律で定められた防火性能と、木材ならではの温かい質感を両立できる点です。
一方、薬剤処理のため通常の木材より価格が高く、重量も増す傾向にあります。
また、薬剤の色が木材の見た目に影響したり、加工性が若干低下したりする点も考慮しておく必要があるでしょう。
【結論】不燃木材はホームセンターでは手に入れにくい

多くの方が気になる、ホームセンターでの不燃木材の入手可否について解説します。
- 主要ホームセンターの取扱状況と在庫がない理由
- 専門的な知識と加工が必要な理由
実際の店舗や通信販売での取り扱い状況などを見ていきましょう。
主要ホームセンターの取扱状況と在庫がない理由
不燃木材は専門的な建材であり、一般的なホームセンターではほとんど取り扱いがありません。
一部の大型店や、プロ向けの資材館では取り寄せ対応をしている場合もありますが、常時在庫を置いている店舗は非常に少ないのが現状です。
これは、不燃木材が高価であり、需要が限られているためです。
なぜDIYでの使用が難しいのか?専門的な知識と加工が必要な理由
不燃木材は、単に切るだけでなく、建材として正しく機能させるために専門的な知識と加工技術が必要です。
例えば、認定番号の確認や、使用場所の建築基準法の制限への理解が求められます。
また、薬剤処理されているため通常の木材とは異なる加工が必要です。
専門業者に依頼することで、これらの問題をクリアし、より安全に施工ができます。
ホームセンター以外の不燃木材の入手方法

最寄りのホームセンターで希望の不燃木材が見つからなかった場合でも、諦める必要はありません。
専門家が利用する建材店や、品揃えが豊富な通信販売など、他の入手経路も存在します。
- 建材店・木材専門店に相談する
- 通信販売を利用する
- 製造元に直接問い合わせる
それぞれの特徴を知りましょう。
建材店・木材専門店に相談する
建築の専門家が利用する建材店や木材専門店では、多種多様な不燃木材を取り扱っています。
専門的な知識を持つ店員に相談できるため、用途に最適な材料を提案してもらえるのが大きな利点です。
ただし、事業者向けの販売が主で、個人への少量販売には対応していない場合もあるため確認が必要です。
オンライン通販(建材ECサイト)を利用する
近年は、建材を専門に扱う通信販売サイトも増えています。
店舗に足を運ぶ手間なく、豊富な種類の中から価格を比較して選べるのが魅力です。
ただし、実物を確認できない点や、木材は重量があるため送料が高額になりやすい点には注意が必要です。
寸法や仕様をよく確認してから注文しましょう。
プレカット工場やメーカーに直接問い合わせる
特定の製品を使いたい場合や、まとまった量が必要な場合は、不燃木材の製造元に直接問い合わせる方法もあります。
地域の販売代理店を紹介してもらえたり、技術的な質問に直接答えてもらえたりする可能性があります。
ただし、個人への直接販売は行っていないことが多いです。
ホームセンターで手に入れにくい不燃木材の種類

ホームセンターでは不燃木材がなかなか入手できません。しかし専門業者では多くの不燃木材の取り扱いがあります。
- 杉(スギ)
- 桧(ヒノキ)
- 合板・ベニヤ
ここではホームセンターでは手に入りにくい不燃木材の樹種と特徴について解説します。
不燃木材で角材を作る方法|種類や選び方、具体的な加工方法など
杉
杉は国産材の中でも代表的な木材で、材質が柔らかく加工しやすいのが大きな特徴です。
木目がまっすぐで美しく、和風・洋風どちらのデザインにも調和します。
他の木材に比べて比較的価格が手頃なため、日曜大工で広い面積に使う場合にも選びやすい木材と言えるでしょう。
桧
桧は光沢のある美しい木肌と、特有の良い香りが魅力の高級材です。
耐久性や耐水性にも優れているため、古くから神社仏閣の建材としても使われてきました。
不燃処理を施すことで、水回りや火の気の近くでも、その上質な風合いを安心して楽しむことができます。
合板・ベニヤ
合板やベニヤは、薄く切った木材を何層にも重ねて貼り合わせたものです。
反りや伸縮が少なく、寸法が安定しているのが利点です。
広い面積を均一に仕上げるのに適しており、壁や天井の下地材、または表面に化粧板を貼った仕上げ材として、不燃仕様のものが広く利用されています。
失敗しない!不燃木材の選び方と専門業者に依頼する際のポイント

不燃木材は安全に関わる重要な資材です。専門家へ依頼する場合でも、購入時に後悔しないために、確認すべき大切な点があります。
- 必ず確認!「不燃材料認定番号」の表示
- 用途に合った種類と寸法を選ぶ
- 自分で加工する際の注意点
認定の表示や用途に合った選び方、そして専門家に依頼する際のポイントをしっかりと押さえておきましょう。
必ず確認!「不燃材料認定番号」の表示
最も重要なのが、国土交通大臣が認定したことを示す表示の確認です。
製品には認定シールが貼られているか、認定番号が印字されています。
この表示がない木材は、法的な不燃材料として認められません。
購入時には必ずこの「不燃認定マーク」や「認定番号」の有無を自分の目で確かめてください。
用途に合った種類とサイズを選ぶ
不燃木材をどこに使うかによって、選ぶべき種類や厚みが変わります。
例えば、建築基準法で内装制限が定められている壁や天井に使うのか、あるいはコンロや薪ストーブの周りに装飾として使うのかで、求められる性能や寸法が異なります。
使用する場所の条件を事前に調べておくことが大切です。
専門業者に相談することの重要性
不燃木材を扱う際は、単に材料を入手するだけでなく、正しい知識を持つ専門家に相談することが非常に重要です。
認定された製品を正しく使用し、建物の防火性能を確保するためには、プロの助言が不可欠です。
専門業者に依頼することで、用途に合った最適な材料選びから、安全な施工までを任せることができ、安心につながります。
不燃木材に関するFAQ(よくある質問)

ここでは、不燃木材を使用する際によく寄せられる疑問にお答えします。
塗装は可能なのか、切断した面の性能はどうなるのかなど、購入前や使用前に知っておくと安心な情報をまとめました。
ぜひ参考にしてください。
不燃木材は自分で塗装しても大丈夫ですか?
塗装は可能ですが、使用する塗料に注意が必要です。
一般的な塗料を塗ると、塗膜が燃えることで不燃材料として認められなくなる場合があります。
塗装する場合は、不燃認定を取得した専用の塗料や、性能に影響を与えないとされる塗料を選び、事前に製品の仕様書を確認してください。
カットした断面の不燃性能はどうなりますか?
薬剤を加圧注入している不燃木材は、内部まで薬剤が浸透しているため、切断した面の不燃性能も維持されます。
ただし、施工方法によっては、切断面の処理について規定がある場合も考えられます。
施工する際は、製品の施工要領書などを確認し、定められた方法を守ることが大切です。
普通の木材に塗るだけで不燃化できる塗料はありますか?
「不燃塗料」と呼ばれる製品はありますが、これを塗るだけで木材そのものが法的な「不燃材料」になるわけではありません。
不燃材料の認定は、基材となる木材と塗装の組み合わせで取得されるものです。
表面に塗るだけでは、規定された防火性能を満足させるのは難しいと理解しておきましょう。
まとめ:不燃木材はホームセンターより専門家への依頼が安全かつ確実
不燃木材は、DIYユーザーが手軽に扱えるものではなく、専門的な知識と加工が必要です。
ホームセンターでの入手は困難であり、専門業者への依頼が最も安全かつ確実な方法です。
専門家に相談することで、用途に合った材料の選定から、適切な施工までを任せることができ、安心・安全な空間づくりを実現できます。