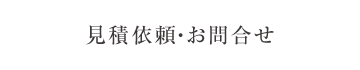トップページ » 不燃木材で角材を作る方法|種類や選び方、具体的な加工方法など
不燃木材で角材を作る方法|種類や選び方、具体的な加工方法など
「商業施設でも無垢木材の角材を使いたいが、内装制限で諦めている」という建築関係者の方は多いのではないでしょうか。
本記事では、建築基準法をクリアしながら木の温もりを表現できる不燃木材角材について解説します。
基本的な種類から樹種選定のコツ、具体的な加工工程、さらに白華現象といった注意点まで、実務に役立つ情報をわかりやすくお伝えします。
不燃木材とは

不燃木材は国土交通大臣認定を受けた防火性能を持つ木材で、不燃薬剤を注入処理することで加熱開始から20分間燃焼しない性能を確保しています。
劇場・商業施設・病院・学校などの特殊建築物の壁材・天井材として使用され、準不燃木材(10分間)や難燃木材(5分間)よりも高い防火性能を持ちます。
準不燃木材との違い
準不燃木材は加熱開始から10分間燃焼しない性能を持つ木材で、不燃木材よりも防火性能は劣りますが、薬剤の含有量が少ないためコストを抑えられます。
主に3階以下の建築物や延床面積が比較的小さい建物で使用され、内装制限の規模に応じて選択されます。
建築物の規模や用途を考慮して適切な防火性能等級を選定することが重要です。
不燃木材の種類

不燃木材は製造方法により大きく2つの種類に分類されます。
最も一般的なのは、無垢材に不燃薬剤を注入する「不燃注入材」です。木材本来の質感や風合いを保持しながら高い防火性能を実現します。
一方、不燃基材に無垢木材突板を貼り合わせた「不燃パネル」は、軽量で施工性に優れている点が特徴です。
また、使用する薬剤によってホウ素系・リン酸系・ケイ酸系に分類され、それぞれ異なる特性を持っています。
角材製造の際は、用途や予算に応じて適切な種類を選択することが重要です。
角材のための不燃木材の選び方

「どの樹種を選べば良いのか」「用途に応じてどんな基準で判断すべきか」など、不燃木材選定で迷う方は少なくありません。
ここでは、角材製造に適した樹種の特徴から、使用用途別の選定ポイントまで詳しく解説します。
樹種で選ぶ
不燃木材の樹種選定では、国産のスギとヒノキが最も実績豊富で信頼性の高い選択肢です。
スギは軽量で加工しやすく、コストパフォーマンスに優れているため、大断面の角材に適しています。
一方、ヒノキは美しい木目と芳香を持ち、高級感のある仕上がりを求める場合に最適です。
スギの場合、赤身部分は薬剤が浸透しにくいため、化粧面には白太材を使用するのが一般的でしょう。
角材の使用用途で選ぶ
角材の使用用途により、求められる防火性能や寸法精度が異なります。
意匠用角材では、美観を重視した樹種選定と表面仕上げが求められます。
また、設置場所の湿度環境を考慮し、白華現象のリスクが高い場所では表面塗装による保護などが必要です。
建築基準法の内装制限要求に応じて、不燃・準不燃・難燃の中から適切な等級を選択することも重要でしょう。
不燃木材を角材に加工する方法

「実際の加工工程はどのような流れなのか」と気になる方も多いはずです。
ここでは、素材選定から最終検査まで、不燃木材角材の製造工程を段階的に解説します。
素材選定
角材用の素材選定では、上小節または無節の高品質材料を厳選します。
スギの場合、薬剤が浸透しにくい赤身部分を避け、化粧面には白太材を使用するのが基本です。
ヒノキでは比較的均一な薬剤浸透が期待できるため、美しい木目を活かした角材製造が可能になります。
素材の含水率や密度も重要な要素で、薬剤の浸透性や最終的な比重に大きく影響します。
また、節や割れなどの欠点部分は事前に除去し、高品質な角材製造の基盤を整える必要があるでしょう。
養生
薬剤含浸後の養生工程は、不燃性能の安定化に欠かせない重要な工程です。
10日〜2週間にわたって屋外環境で薬剤を木材内部に定着させ、均一な分布を確保します。
養生不足は白華現象や性能低下の原因となるため、十分な時間を確保することが重要です。
また、材料の積み重ね方法や間隔も薬剤の均一な定着に影響するため、専門的な管理技術が求められるでしょう。
乾燥
養生完了後は、低温乾燥により水分を除去します。
急激な乾燥は割れや反りの原因となるため、温度管理を徹底した乾燥炉での処理が必要です。
角材の場合、断面が大きいため内部まで均一に乾燥させるには時間をかけた工程が欠かせません。
乾燥完了時の含水率は、最終製品の品質と寸法安定性に直結するため、定期的な測定と管理が重要になります。
適切な乾燥により、薬剤の定着が確実になり、長期間にわたって安定した不燃性能を維持できるでしょう。
加工
乾燥完了後、設計図面に基づいて角材の断面形状と長さに加工します。
不燃木材は通常の木材よりも比重が高いため、加工時の切削抵抗や工具摩耗に注意が必要です。
精密な寸法精度を確保するため、適切な切削条件の設定と工具の定期的なメンテナンスが欠かせません。
また、加工時に発生する切りくずや粉塵には薬剤成分が含まれているため、作業環境の安全対策も重要な要素となります。
加工後は表面の仕上がり状態を確認し、必要に応じて追加加工を実施するでしょう。
仕上げ・検査
最終工程では、サンダー仕上げによる表面平滑化と、必要に応じたウレタン塗装を実施します。
塗装は白華現象の抑制と美観向上の両方に効果的で、特に角材では表面積が大きいため重要な工程です。
重量測定管理により規定比重の達成を確認し、場合によってコーンカロリーメータによる発熱性試験で不燃性能を検証します。
梱包前の最終検品では、寸法精度・表面品質・欠点の有無を詳細にチェックし、品質基準をクリアした製品が出荷されます。
不燃木材加工で起きる白華現象とは

白華現象とは、不燃薬剤の成分が木材の吸湿・放湿により表面に析出する現象で、不燃木材特有の課題です。
常に外気にさらされる場所や多湿な環境では発生リスクが高まり、美観を損なう原因となります。
特に角材は表面積が大きいため、白華現象の影響がより顕著に現れる可能性があります。
予防策としては、不燃木材専用塗料ウレタン塗装による表面コーティングが有効です。
これにより薬剤の表面への析出を物理的に防げます。
すでに白華現象が発生している場合は、固く絞った雑巾で拭き取ることで一時的な改善は可能ですが、根本的な解決には表面保護塗装の施工が必要です。
まとめ
不燃木材を角材に加工する技術は、建築物の木質化推進において重要な役割を果たしています。
適切な樹種選定から厳格な加工工程管理まで、各段階での品質確保が高性能な製品製造の鍵となります。
白華現象などの課題はありますが、表面塗装などの対策により解決可能です。
建築基準法の内装制限をクリアしながら、無垢木材の温もりを建築空間に取り入れられる不燃木材角材は、今後さらなる需要拡大が期待される建築材料といえるでしょう。