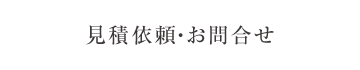トップページ » 準不燃木材の加工は可能?切断・塗装時の注意点と認定への影響を徹底解説
準不燃木材の加工は可能?切断・塗装時の注意点と認定への影響を徹底解説
この記事では切断や塗装時の注意点、防火認定への影響を解説します。
安全に加工する方法から専門業者への依頼方法まで、知りたい情報を網羅しました。
認定が無効になるケースやよくある質問にも回答。正しい手順を理解し、準不燃木材を有効活用しましょう。
準不燃木材とは?基本的な定義と加工前に知るべきこと

準不燃木材は、建築基準法で定められた防火木材です。
加工を検討する前に、その定義や他の木材との違い、認定の仕組みといった基本的な知識を理解しておくことが重要です。
詳しく見ていきましょう。
準不燃木材の定義と建築基準法での位置づけ
準不燃木材とは、加熱開始後10分間、燃え広がりにくく、防火上有害な損傷が生じない性能を持つと定められた木材です。
建築基準法では内装制限のかかる部位などに使用が認められており、安全な空間づくりに貢献します。
国土交通大臣の認定を受けたものだけが準不燃木材と認められます。
準不燃木材とは?不燃木材との違いやメリット・デメリットなど解説
不燃木材・難燃木材との違い
防火木材は性能順に不燃・準不燃・難燃の3つに区分されます。
加熱開始後、不燃は20分、準不燃は10分、難燃は5分間燃焼しないことが基準です。
準不燃木材は、木材の質感を活かしつつ、難燃木材より高い防火性能を持つ木材として、多くの建築物で採用されています。
準不燃木材の認定の仕組み
準不燃木材の認定には、メーカーごとに製品を審査する「個別認定」と、定められた仕様に基づき製造する「仕様規定」があります。
市場に流通する多くは個別認定品です。
加工の可否や範囲は、この認定内容によって大きく異なるため、使用前に必ず認定書を確認する必要があります。
準不燃木材の加工は原則可能!ただし認定の維持に注意

準不燃木材は加工できますが、防火性能の認定を維持するには注意が必要です。
なぜ加工に注意が必要で、何を確認すべきなのでしょうか。
現場加工と工場加工の違いも含めて、安全に加工するためのポイントを解説します。
なぜ準不燃木材の加工には注意が必要なのか
準不燃木材は、薬剤注入や基材との組み合わせで防火性能を確保しています。
切断や塗装などの加工によって、その性能が損なわれる可能性があるためです。
認定された仕様から外れる加工を行うと、準不燃木材として認められなくなり、法的な問題に発展する恐れがあるため注意が必要です。
「認定書」の確認が最も重要
準不燃木材を加工する際は、必ず国土交通大臣が発行した「認定書」の確認が不可欠です。
認定書には、加工の許容範囲(切断、塗装、釘打ちなど)が詳細に記載されています。
この内容を遵守することが、防火性能を維持し、法令に適合させるための絶対条件となります。
現場での加工と工場での加工の違い
現場での加工は、認定書で認められた軽微な切断などに限定される場合がほとんどです。
一方、認定を受けた工場では、より広範囲な加工が可能です。
複雑な形状や塗装を施したい場合は、認定工場を持つメーカーや専門業者に依頼するのが確実で、品質と性能の維持につながります。
【種類別】準不燃木材への代表的な加工方法と注意点

準不燃木材には、切断や塗装などさまざまな加工が考えられます。
しかし、どの加工にも認定を維持するための注意点が存在します。
ここでは代表的な加工方法を取り上げ、それぞれで守るべきポイントを具体的に解説するので、ぜひ参考にしてください。
乾燥
木材選定後、薬剤処理に適した含水率まで乾燥させる工程が必要です。
薬剤の浸透性を高め、均一な処理を行うために重要な段階といえます。
自然乾燥と人工乾燥を組み合わせながら、木材の特性に応じた条件を設定します。
急激な乾燥は木材の割れや反りの原因となるため、慎重な温度・湿度管理が求められるでしょう。
切断・切削
乾燥が完了した木材は、用途に応じて適切なサイズに切断・切削されます。
羽目板やルーバーなど、使用目的に合わせた形状に仕上げていく工程です。
薬剤処理における品質にも影響を与えるため、精密な寸法管理が必要になります。
また、表面の仕上げ精度も重要で、薬剤の浸透性や見た目の美しさに大きく関わる作業といえます。
加圧注入
準不燃木材製造の中心となる工程が薬剤の加圧注入です。
配合された不燃薬剤を、規定する木材の比重となるよう加圧しながら注入していきます。
真空状態にした木材に薬剤を注入し、加圧により木材内部まで薬剤を浸透させる仕組みです。
注入量や圧力、時間などの条件を厳密に管理することで、均一な処理が可能になります。
後乾燥
薬剤注入後、薬剤を木材内部に定着させるための乾燥工程が行われます。
約2週間の養生期間を経て、低温乾燥炉で水分を除去する作業です。
急激な乾燥は薬剤の偏在や木材の変形を招くため、温度管理が重要になります。
この工程により、準不燃性能を安定的に発揮できる製品が完成するでしょう。
検品
最終工程では、厳格な品質検査が実施されます。
木材の重量を1本ずつ計測し、規定通りの比重になっているかを確認する作業です。
必要に応じてコーンカロリーメータによる燃焼試験も行われ、不燃性能が基準を満たしているかを検証します。
準不燃木材の加工が防火性能の認定に与える影響

準不燃木材への加工は、防火性能の認定に直接関わります。
どのような場合に認定が無効となり、どうすれば認定を維持できるのでしょうか。
ここでは、加工と認定の関係性に焦点を当て、法規を守るための重要なポイントを解説します。
加工によって認定が無効になるケース
認定書で定められた範囲を超える加工を行った場合、準不燃木材としての認定は無効になります。
例えば、指定外の塗料の使用、許容範囲を超える切断、認定外の工場での表面加工などが該当します。
認定が無効になると、建築基準法違反となるため、絶対に行ってはいけません。
認定を維持したまま加工する方法
認定を維持して加工する唯一の方法は、製品ごとの認定書の内容を厳守することです。
許容される加工の種類、方法、使用木材の指定などを正確に把握し、その範囲内で作業を行います。
不明な点があれば、自己判断せず、必ずメーカーや販売元に確認することがトラブルを避ける鍵です。
加工後の再認定や証明書について
一度認定が無効になった木材を、個人や現場で再認定することはできません。
認定工場で適切に加工された製品には、多くの場合、加工後も性能を証明するラベルや出荷証明書が発行されます。
これらが、加工された準不燃木材が法令に適合していることを示す重要な証明となります。
加工済みの準不燃木材を入手する具体的な方法

希望の形状や仕上げに加工された準不燃木材が必要な場合、どこに依頼すればよいのでしょうか。
認定を維持した安全な木材を入手するためには、依頼先の選定が重要です。ここでは、具体的な入手方法と選ぶ際のポイントを紹介します。
認定工場を持つメーカーに依頼する
最も確実な方法は、準不燃木材の認定工場を持つメーカーに直接依頼することです。
製品の特性を熟知しており、認定の範囲内でさまざまな加工に一貫して対応できます。
品質管理が徹底されているため、性能が保証された安全な加工品を確実に入手でき、安心して建築に使用できます。
加工対応可能な専門業者を探す
木材加工を専門に行う業者の中には、準不燃木材の加工に対応している場合があります。
ただし、依頼する際は、その業者が扱う木材メーカーの認定工場であるか、あるいは認定内容を遵守した加工が可能かを必ず確認する必要があります
。実績や証明書の有無を確認することが重要です。
購入時に確認すべきポイント
加工済みの準不燃木材を購入する際は、製品が正規の認定品であることを示すラベルや刻印を確認します。
また、加工内容が認定の範囲内であることを証明する出荷証明書や施工仕様書などの書類を必ず受け取りましょう。
これらの書類は、検査時などに法令適合性を証明するために不可欠です。
準不燃木材の加工に関するよくある質問

ここまで準不燃木材の加工について解説しましたが、まだ疑問点もあるかもしれません。
特に多く寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすく回答します。
DIYでの加工可否や価格など、具体的な疑問をここで解決しましょう。
DIYで準不燃木材を加工できますか?
認定書で許可された範囲の軽微な切断程度であれば可能な場合もありますが、原則として推奨されません。
薬剤の塗布など専門的な処理が必要なケースが多く、知識なく加工すると認定が無効になるリスクが非常に高いです。
安全と法令遵守のため、専門業者に依頼することを強く推奨します。
ホームセンターで購入した準不燃木材は加工しても大丈夫ですか?
ホームセンターで販売されている製品も、加工の可否はメーカーが発行する認定書の内容次第です。
購入時に認定書の写しを入手し、加工の許容範囲を確認する必要があります。
認定書の提示がない、または内容が不明な場合は、安易に加工せず、販売元やメーカーに問い合わせてください。
加工すると価格はどのくらい変わりますか?
価格は加工の内容や複雑さ、依頼する量によって大きく変動します。
単純な切断であれば費用は抑えられますが、特殊な形状や塗装を施す場合は高くなります。
正確な費用を知るためには、希望する加工内容を伝え、メーカーや専門業者に個別に見積もりを依頼する必要があります。
まとめ:安全な準不燃木材の加工と活用のために
準不燃木材の加工は、認定書の遵守が絶対条件です。
木材の美しさと高い防火性能を両立させるためには、正しい知識が欠かせません。
この記事のポイントを再確認し、安全な設計・施工に役立ててください。