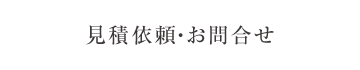トップページ » 不燃木材とは?種類や基準、メリット、難燃木材との違いを徹底解説
不燃木材とは?種類や基準、メリット、難燃木材との違いを徹底解説
商業施設や公共建築物で木の温かみを活かしたい、でも防火性能が心配という方も多いでしょう。
この記事では、安全性とデザイン性を両立できる不燃木材について、種類や基準、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
不燃木材とは

建築業界において、防火性能と美観を両立させる材料として注目を集めているのが不燃木材です。
従来の木材では使用が制限されていた商業施設や公共建築物でも、安全性を確保しながら木の温かみを表現できるようになりました。
ここでは、不燃木材の基本的な定義や建築基準法との関係について解説します。
定義と基準
不燃木材は、国土交通省が定める不燃材料の基準を満たした木材のことです。
具体的には、加熱開始から20分間にわたり総発熱量が8MJ/㎡以下で、燃焼しないこと・有害な変形や損傷を生じないこと・避難上有害な煙やガスを発生させないことの3つの条件を満たす必要があります。
認定を受けるためには、コーンカロリーメータ機による厳格な試験が実施されます。
用途
不燃木材は主に内装材として利用されます。具体的には、羽目板・ルーバー・見切り材などの壁や天井の仕上げ材として活用されています。
特に劇場・病院・学校・大型商業施設など、建築基準法の内装制限がかかる建物での使用が多いです。
ただし、屋外や多湿環境では白華現象のリスクが高まるため、使用は推奨されません。室内の乾燥した環境での使用に適しています。
準不燃木材との違い
準不燃木材は、加熱開始から10分間の耐火性能を持つ材料です。
不燃木材の20分間と比べて半分の時間ですが、その分コストを抑えられます。
総発熱量の基準は不燃木材と同じ8MJ/㎡以下ですが、求められる耐火時間が短いため、比較的軽微な内装制限の場所で使用されます。
建物の用途や規模によって、適切な材料を選択する必要があります。
難燃木材との違い
難燃木材は最も軽い防火基準で、加熱開始から5分間の耐火性能を持ちます。
不燃木材や準不燃木材と比べて要求される性能は低いものの、無処理の木材よりも火災リスクを軽減できます。
住宅など比較的小規模な建物や、内装制限の対象外となる部分での使用が一般的です。
防火性能とコストのバランスを考慮して選択されることが多い材料です。
不燃木材の種類とは

一口に不燃木材といっても、実は製造方法や構造によっていくつかの種類に分けられます。
それぞれの種類には独自の特徴があり、使用する環境や求められる性能によって適切な選択が変わってきます。
設計や施工を進める上で、どの種類が目的に適しているかを理解することは重要です。ここでは、不燃木材の製造方法による種類の違いについて解説します。
注入材
注入材は、無垢材にホウ酸系やリン酸系の不燃薬剤を加圧注入して製造されます。
木材本来の質感や触り心地を保ちながら、高い防火性能を実現可能です。
スギやヒノキなど国産材を使用することが多く、厚さ12mm以上から認定を取得できます。
表面の木目や色合いは天然木そのもので、高級感のある仕上がりになります。
ただし、薬剤の影響で無処理材よりもやや重くなり、白華現象のリスクがあるため注意が必要です。
不燃ボード
不燃ボードは、ダイライトなどの不燃性基材に0.2mm程度の薄い突板を貼り合わせた材料です。
薬剤を使用していないため白華現象の心配がなく、メンテナンスが容易です。
多様な樹種の突板を使用できるため、デザインの自由度が高く、オリジナリティのある空間を演出できます。
厚さ6mmから製造可能で軽量なため、細かい納まりにも対応しやすく、施工性に優れています。質感は注入材よりもやや硬めです。
不燃木材のメリットとは

建築材料を選定する際には、防火性能に加えて、美観、コスト、施工性など、さまざまな要素を総合的に考慮する必要があります。
不燃木材は、従来の建材では実現が難しかった多くの利点を備えており、特に内装制限のある建物において木質化を検討する設計者や施工業者にとって、非常に魅力的な選択肢です。
ここでは、不燃木材を採用することで得られる主なメリットについて解説します。
天然木が使える
不燃木材を使用することで、内装制限の対象となる建物でも本物の木材を使用できます。
プリント化粧板や樹脂製の代替材と異なり、天然木ならではの木目の美しさや質感を表現可能です。
スギやヒノキなどの国産材を使用した場合、木の香りも楽しめるだけでなく、リラックス効果も期待できます。
商業施設や教育施設において、人工的な材料では表現できない自然な温かみのある空間を作り出せます。
有毒ガスが出ない
火災発生時に不燃木材が燃えた場合でも、有害なガスが発生しません。
樹脂系の材料と異なり、天然木が原料であるため、燃焼時の安全性が高いのが特徴です。
避難時の煙による被害を最小限に抑えるため、人命安全の観点から重要なメリットといえます。
特に多くの人が利用する公共施設や商業施設では、避難時の安全性確保が重要であり、不燃木材の採用により安心して木質化を進めることが可能です。
不燃木材のデメリットとは

どの建材にもメリットがある一方で、注意すべき点やデメリットが存在します。
不燃木材も例外ではなく、採用を検討する際には事前にリスクや制約を理解しておくことが重要です。
ここでは、不燃木材を使用する際に注意すべきデメリットについて解説します。
白樺現象が起きる
白華現象とは、不燃薬剤に含まれる成分が木材の表面に白い結晶として析出する現象です。
これは、空気中の湿気を吸収した薬剤が木材表面に浮き出ることで発生し、特に湿度の高い環境で起こりやすくなります。
防火性能には影響しないものの、外観上の問題として美観を損なう可能性があるため注意です。
対策としては、木材表面に不燃塗装を施すことで発生を防止できます。
また、白華現象が発生した場合でも、固く絞った布で拭き取ることで除去が可能です。
現場塗装が難しい
不燃木材の防火性能を維持するためには、均一な塗膜厚さを保った塗装が必要です。
現場での塗装では、環境条件や施工技術のばらつきにより、均一な仕上がりを確保することが困難です。
そのため、品質の高い仕上がりを求める場合は、工場での塗装が推奨されます。
工場塗装により、安定した品質と防火性能を確保できますが、納期やコストに影響する場合があります。
計画段階から塗装仕様を検討することが重要です。
不燃木材の作り方とは

不燃木材の品質や性能は、製造工程に大きく左右されます。
適切な材料選択や施工計画を立てるためには、どのような工程を経て製品が作られるかを理解することが重要です。
ここでは、不燃木材がどのような工程で製造されているかについて解説します。
注入材
注入材の製造は、まず上小節または無節の高品質な原木を選定することから始まります。
次に、配合された不燃薬剤を規定の比重となるよう木材内部に加圧注入します。
薬剤含浸後は約2週間の養生期間を経て、低温乾燥炉で約2週間かけて水分を除去。
その後、1本ずつ重量を計測して規定通りの比重を確認し、指定の断面形状に加工します。
最終的にサンダー仕上げと塗装を行い、コーンカロリーメータ機で性能確認を実施してから出荷されます。
不燃ボード(練付材)
不燃ボードの製造は、使用する樹種の選定から始まります。ナラ・タモ・ウォールナットなど、多様な樹種から0.2mm程度の極薄突板を作成します。
次に、ダイライトやケイカル板などの不燃性基材の上に突板を接着剤で練り付けます。
その後、プレス機で圧着して一体化させ、正寸カットと研磨を行います。
最終工程では、ウレタン樹脂系塗装を施して完成です。不燃液を使用しないため、液垂れや白華現象の心配がなく、安定した品質を確保できます。
まとめ

不燃木材は、建築基準法の内装制限がある建物でも天然木を使用できる画期的な建材です。
注入材と不燃ボードの2種類があり、それぞれ異なる特徴があります。
天然木の美しさを保ちながら高い防火性能を実現できる一方で、白華現象や現場塗装の困難さなどのデメリットもあります。
適切な材料選択と施工により、安全性とデザイン性を両立した魅力的な空間を創造できるでしょう。