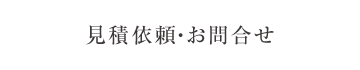トップページ » 不燃木材の板の選び方|用途・法律・メンテナンスをわかりやすく解説
不燃木材の板の選び方|用途・法律・メンテナンスをわかりやすく解説
建築物の防火性能を高めながら、木材本来の温もりと美しさを実現する不燃木材の板。
本記事では、不燃木材の基礎知識から選び方のコツ、メンテナンス方法まで実践的な情報をまとめました。
【基礎知識】そもそも不燃木材とは?安全な板の活用法

不燃木材の基本的な仕組みと、防火性能による等級の違いについて詳しく見ていきましょう。不燃木材を正しく選ぶためには、まず基礎的な知識を身につけることが重要です。
不燃木材の定義と仕組み
不燃木材とは、天然木材に特殊な薬剤を含浸させることで、火災時の燃焼を抑制する性能を持たせた建築材料のことです。
一般的な木材は可燃性で火災時に燃え広がりやすいという課題がありますが、不燃処理により炎に触れても炭化する速度を遅らせ、燃焼の拡大を防ぐ効果が得られます。
不燃・準不燃・難燃の違いを一覧で比較
防火性能を持つ木材は、国土交通大臣が定める基準により3つの等級に分類されています。等級が高いほど火災リスクを軽減する効果が大きく、建築基準法で定められた内装制限にも対応できる範囲が広がります。
|
種類 |
不燃性能の継続時間 |
総発熱量 |
主な用途 |
|
不燃木材 |
加熱開始後20分 |
8MJ/平方メートル以下 |
高層建築物、大規模商業施設 |
|
準不燃木材 |
加熱開始後10分 |
8MJ/平方メートル以下 |
中規模商業施設、オフィスビル |
|
難燃木材 |
加熱開始後5分 |
8MJ/平方メートル以下 |
小規模店舗、住宅の一部 |
これらの性能は、コーンカロリーメータ機による厳格な試験で測定されます。
試験では実際に火炎を当てて、燃焼しないこと、有害な変形や損傷が生じないこと、避難に支障をきたす煙やガスが発生しないことを確認します。
板材を選ぶ際は、設置場所の法的要件に応じて適切な等級を選択することが不可欠です。
不燃木材が必須な場所|内装制限と板の規定

建築基準法では、火災時の安全性を確保するため、建物の用途や規模に応じて内装材に制限を設けています。不燃木材の板を使用する場面を正しく理解しましょう。
内装制限とは?対象となる建築物と部位
内装制限は、建築基準法第35条の2に基づき、火災時の延焼防止と避難安全性を確保するための規制です。
多数の人が利用する建築物や、火災リスクが高い建築物では、壁や天井の仕上げ材に不燃材料や準不燃材料の使用が義務付けられています。
対象となる主な建築物には、劇場や映画館、百貨店、飲食店、ホテル、病院、学校、集会場などがあります。
建物の規模や階数によっても制限内容が変わり、例えば3階以上の部分や地下街、無窓階などは特に厳格な基準が適用されます。
防火地域・準防火地域での木材利用のルール
都市計画で定められた防火地域や準防火地域では、建築物の構造や材料についてより厳しい制限が設けられています。
防火地域では、原則として耐火建築物または準耐火建築物の建設が義務付けられており、外壁や軒裏についても不燃材料の使用が求められます。
内装についても厳格な制限があり、壁や天井には不燃材料または準不燃材料の使用が必要になる場合が多くあります。
準防火地域では、建物の規模や構造に応じて段階的な制限が適用されます。
木造建築物でも一定の条件下で建設可能ですが、外壁の開口部や屋根材については防火性能を持つ材料の使用が必要です。
不燃木材のメリット・デメリット|後悔しない板選びの知識

不燃木材の板にはどのような長所と短所があるのでしょうか。導入前に知っておくべきポイントを詳しく解説します。
不燃木材を板として使うメリット
不燃木材の板が注目される理由は、安全性とデザイン性を両立できることにあります。ここでは3つの主要なメリットについて詳しく見ていきましょう。
木の質感・温もりはそのままに高い防火性能を実現
不燃木材の最大の魅力は、天然木材の美しさと触り心地を保ちながら、優れた防火性能を発揮することです。
薬剤処理を施しても木目の美しさや自然な色合いはそのまま残り、手で触れた時の温かみや心地よい感触も変わりません。
木材特有の調湿効果も維持されるため、室内の湿度を適切に保ち、結露やカビの発生を抑制する効果が期待できます。
内装制限がある場所でも自由に木質化できる
従来は法的制限により木材の使用が困難だった場所でも、不燃木材の板なら安心して木質化を進められます。
商業施設の壁面や天井、公共建築物のエントランス、飲食店の内装など、多くの人が利用する空間で木の温もりを表現できるようになります。
建築確認申請や消防検査もスムーズに進むため、設計段階での制約が少なく、デザイナーや建築家の創造性を発揮しやすくなります。
空間の意匠性・デザイン性を高められる
不燃木材の板は、空間デザインの幅を大きく広げる効果があります。
木材ならではの自然な表情と温かみが、無機質になりがちな商業空間や公共空間に人間味と親しみやすさをもたらします。
樹種や仕上げ方法の組み合わせにより、モダンからクラシックまで幅広いデザインテイストに対応できます。
板の張り方向や配置パターンを工夫することで、空間に動きやリズムを生み出し、視覚的な興味深さを演出できます。
不燃木材を板として使うデメリット
メリットが多い不燃木材ですが、いくつかの課題や注意点も存在します。導入前に理解しておくべきデメリットを見ていきましょう。
導入コストが割高になる傾向
不燃木材の板は、薬剤処理や品質管理のコストが製品価格に反映されるため、一般的な木材と比較して割高になる傾向があります。
材料費だけでなく、専門的な施工技術が必要なため工事費も上昇する場合があります。
薬剤含浸により重量が増加するため、運搬費や荷上げ費用も通常より高くなります。
また、下地の補強が必要になるケースもあり、全体的な工事費の増加要因となります。
特に大規模な面積に使用する場合は、予算への影響が大きくなるため慎重な検討が必要です。
経年による見た目の変化(白華)が起こる場合がある
不燃木材特有の問題として白華現象があります。
これは木材内部の不燃薬剤成分が湿気の影響で表面に染み出し、白い粉状の結晶となって現れる現象です。
性能には影響ありませんが、木目が曇って見えるため美観が損なわれる可能性があります。
加工やメンテナンスに専門知識が必要
不燃木材の板は、薬剤処理により一般的な木材とは異なる特性を持つため、加工や施工には専門的な知識と技術が求められます。
現場での微調整やカット作業も、薬剤の効果を維持するための適切な方法で行う必要があります。
失敗しない不燃木材の選び方|理想の板を見つけるポイント

不燃木材の板選びで失敗を避けるためには、複数の観点から検討することが重要です。樹種、認定、仕上げ、メーカーの4つのポイントについて詳しく解説します。
樹種で選ぶ(スギ、ヒノキ、レッドシダーなど)
不燃木材の板選びにおいて樹種の選択は、デザイン性と機能性の両面で重要な要素です。
代表的な樹種として、スギは軽量で加工しやすく、柔らかな木目が特徴的です。
色合いは淡い黄白色から薄いピンク色まで幅があり、ナチュラルな空間演出に適しています。
ヒノキは高級感のある美しい木目と独特の芳香が魅力で、抗菌・防虫効果も期待できます。
色合いは淡い黄色から薄い褐色で、時間とともに深みのある色調に変化します。
レッドシダーは赤みがかった美しい色合いと直線的な木目が特徴で、モダンなデザインにも調和します。
天然の防虫・防腐効果があり、メンテナンス性に優れています。
認定番号(国交省認定)を必ず確認する
不燃木材の板を選ぶ際、国土交通大臣認定番号の確認は絶対に欠かせません。
認定番号は樹種、板厚、塗装の有無など具体的な条件と紐づいているため、使用予定の仕様が認定範囲内にあるかを慎重にチェックする必要があります。
塗装仕上げを行う場合は、塗装認定を取得した製品を選ぶ必要があります。
塗装認定では、特定のウレタン樹脂系塗装との組み合わせで性能が保証されているため、塗装材の種類や施工方法も認定条件に従う必要があります。
建築確認申請時には認定番号を明記するため、事前の確認が不可欠です。
塗装や仕上げ(クリア、カラー)の種類で選ぶ
不燃木材の板は、仕上げ方法によって外観や性能が大きく変わります。
クリア塗装は木材本来の色合いと木目を最大限に活かす仕上げ方法で、天然木の美しさを重視する空間に適しています。
透明度の高いウレタン塗装により表面を保護し、汚れや傷から守る効果があります。
カラー塗装では、着色により空間のコンセプトに合わせた色調に調整できます。
落ち着いたブラウン系から明るいナチュラル系まで幅広い選択肢があり、インテリアデザインの自由度が高まります。
ただし、塗装を行う場合は塗装認定を取得した製品を選ぶ必要があります。
信頼できるメーカーの特徴を比較する
不燃木材の品質は、メーカーの技術力と品質管理体制に大きく左右されます。
信頼できるメーカーの特徴として、まず国土交通大臣認定を多数取得していることが挙げられます。
認定取得には厳格な試験をクリアする必要があり、技術力の証明となります。
品質管理体制の充実も重要なポイントです。
コーンカロリーメータ機などの専用試験機器を保有し、社内で継続的な品質検査を実施しているメーカーは信頼性が高いといえます。
製造工程の管理体制や検査記録の保管状況も品質の指標となります。
不燃木材や板に関するQ&A

不燃木材の板について、よくある質問と回答をまとめました。導入前の疑問解決にお役立てください。
シロアリ対策は必要ですか?
不燃木材に使用される薬剤の多くは、防蟻効果も兼ね備えているため、通常の木材よりもシロアリ被害のリスクは大幅に軽減されます。
リン酸系やホウ酸系の薬剤は、シロアリが嫌う成分を含んでおり、摂食行動を抑制する効果があります。
ただし、完全にシロアリ被害を防げるわけではないため、建物全体の防蟻対策との組み合わせが重要です。
特に土台や柱などの構造材についてはJAS規格に基づく防蟻処理を施すことが推奨されます。
メンテナンス方法や耐用年数を教えてください。
不燃木材の板は適切なメンテナンスにより、20年から30年程度の耐用年数が期待できます。
日常的なメンテナンスとしては、乾いた布や掃除機による埃の除去、固く絞った布での水拭きが基本となります。
年1回程度の定期点検では、白華現象の有無、塗装の剥がれや傷、変色などを確認します。
カットなどの現場加工はできますか?
不燃木材の板は現場での加工が可能ですが、薬剤の効果を維持するための注意点があります。
カットや穴あけなどの加工により薬剤が浸透していない内部が露出する場合は、露出部分への薬剤の補塗が必要になることがあります。
デザイン性と安全性を両立する不燃木材の板を選ぼう
不燃木材の板は、建築基準法の内装制限をクリアしながら木材本来の美しさと機能性を活かせる優れた建材です。
樹種の選択から認定番号の確認、仕上げ方法の検討まで、多角的な視点での選択が成功の鍵となります。
初期コストは割高になりがちですが、長期的な安全性とデザイン性の両立により、建物の価値向上と利用者満足度の向上が期待できます。
信頼できるメーカーと施工業者を選び、建物の用途と環境に最適な不燃木材の板を選択しましょう。